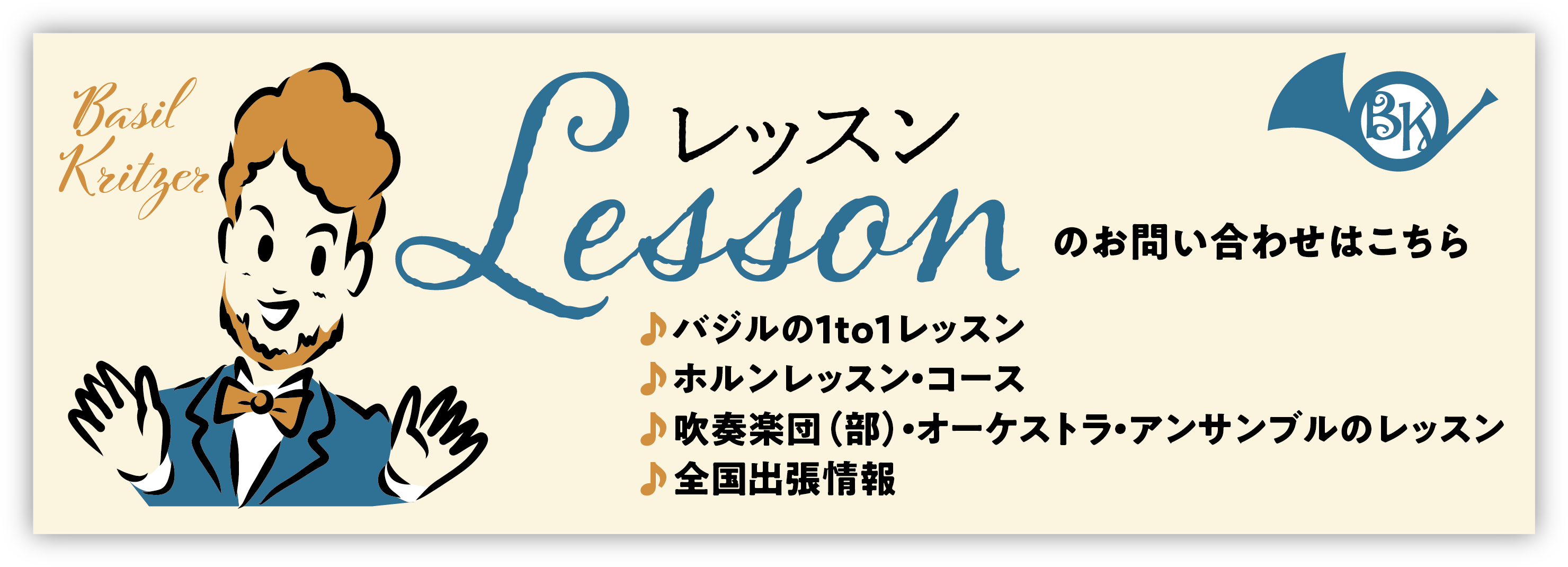目の前に大きな五線譜を想像して、大きなハイCの音符を想像する。
その音符と目を合わせ、そこだけを見て、ハイCのことだけを考えて吹く。
方法は考えない。
身体の感覚も意識しない。
すると、ハイCがずっと苦手だったその生徒さんは、スパンと完璧で軽快なハイCが吹けた😯
・・・吹く直前、不安そうな表情。縮こまった身体。
なのに、だ!
わたしのなんとなくの予想に反し、本人の予想にも反し、だ!
生徒さんが、自身の自由意志による創造的なソルフェージュ(ハイCをイメージし、集中する)を行い、その生徒さん固有の身体と自らの神経系により、その方にとっての最高の奏法を生み出した瞬間だ。
どんな奏法テクニック論、どんな身体の使い方論からも決して導き出せない、オーガニックな奏法だ!
同じアプローチで、こんどは力強いハイFが鳴らせた。
今まで1度も出来なかったようなことができた。
本人の身体で、本人の運動能力と神経系の力で。
奏法論は、その人がその人自身にとって不利なやり方へと脱線しているのを、その人にとって本来持つはずの有利なやり方へと軌道修正するのが役割ではないだろうか。
奏法論は、その大まかな像を推測するまでが出来ることで、『実物』を正確には描写することは多分できない。当てはめ押しつけることなんてもっとできない。
『これだけが正しい』と規定された像へと他者の運動を矯正することを主な方法論とした奏法論は、その矯正が機能しないケースや有害な影響をもたらしているケース(それは決して少なくなく、珍しくない)を否認することで保存されているのではないか?
奏法論や解剖学的運動力学的モデルも推測のや大まかな描写の域を出ず、
演奏は演奏する本人の神経系により実現され、
運動と奏法は本人のソルフェージュを通じてその本人の身体に最適なものへと100%本人の力により形成される。
このように全てを生徒自身・吹く人自身の能力へ帰することを前提にせず、仮説や自論を生徒自身・吹く人自身の上位に置いてしまうと、様子がおかしくなっていくのかな、そんな気がし始めている。