わたしが奏法の話をするときは「中和解毒剤」として用いている、というところからの続き。
【血清的奏法論】
中和しようというからには、毒がある。
その毒とは、奏法論。
どうして奏法論が毒になるのか?
奏法論が「正しい(or良い)やり方」を狭めて定義しようとするから。
薬にも合う合わないがあるように、奏法論にも合わう合わないがある。それは、奏法論が現実の多様性を汲み取りきれないからだ。
薬に合う合わないがあるように、奏法論も万能薬ではない。なのに、万能薬かのように用いようとして、現実を奏法論に合わせようとして、合わない事例や逆効果になる実態を否定すり。
この実態の否定が「毒」。
その毒を中和する。
では、中和しきったらそこに残るのは何か?
実態や真実が残るのではないか。
その実態・真実に根ざした「楽器はどうすれば吹けるのか?」の論は何だろうか?
そこにアーノルド・ジェイコブスの哲学は肉迫しているのかもしれない。
「歌うこと」
「奏でたい音色をありありと思い浮かべること」
「語りたい音楽を自らのうちに創り、それをたまらわずに言い切ること」
ボディマッピングやアンブシュアタイプ研究や解剖学的な呼吸理解などは効果的な解毒剤。
ジェイコブスの哲学やアレクサンダーテクニークの論理は、実態や真実に近い故の解毒効果もあるが、本質的には「楽器でやりたいことはどうすればやれるか?」の構築的方法論として位置づけられるのではないか。
このように考え始めている。


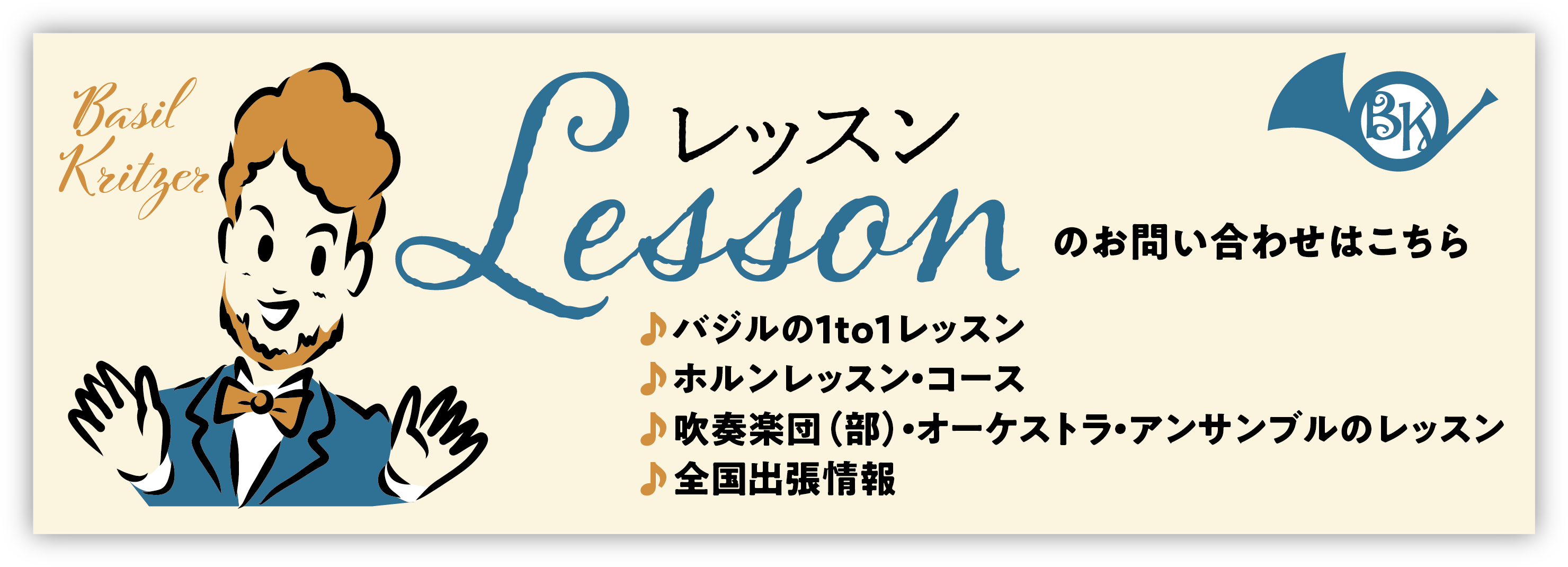
とても興味深い内容でした。1つ今悩んでいることがあります。伝え方の問題です。
音を押し出して吹いてしまうのは正しくない、息はまっすぐ入れる、と専門的に師匠から色々と教わりました。(細かい表現の話はまた別です。)
愛好家の中には学生時代に先輩から教わったり、独学で学ばれた方が多くいます。それ故か、時々、表現する・歌う=音をフレーズの終わりに向かって押し出して吹いてしまう人(Tp、Cl)がいるのですが、どうも癖になっているようです。
のびのびとした表現、演奏をするために、まっすぐ息を入れてそのまま素直に吹いてもらいたいのですが
癖になっている場合、どのようなアクションが必要でしょうか。
教える立場なのでそのままにも伝える必要があるのですが、そういうのも今時は余計なアドバイスなのでしょうか。
素直に奏でると言うより、本人が失敗できない、と思ったり、目立ちたさもある人の場合、音量や音程をやたらと上げてしまうようで、それらも押し出しに繋がってしまい、なんだかわざとらしい演奏になってしまっているのです。
ある奏法が正しい正しくないと言う話というよりも、感覚的なものもあると思いますが、クレッシェンドではない部分で一音一音をぶわあっと押し出して吹かれると気持ちが悪くなる感じがします。これは何故なのでしょう。
最初から吹き込むわけではなく、徐々に押し出していると言う表現が的確でしたので、そのように描写しました。
指揮をする側として、修正する時には肯定形を使うようにしていますが、まずは一度、こういうやり方もありますが、やめておきましょう。なぜならこうだから、もっとこういう風にするとより良くなるかもしれません。どう違うのか実験してみましょう。と実証したやり方も心がけています。
ある程度の年齢になった社会人の場合、伝え方に関して考えたり表現を変えることが増えました。
全体の音楽の向上のための良いアイデアを模索中です。
伝え方の前に、必要要件に目を向けると良いかもしれません。
・後押しではなくまっすぐが良いという価値観が相手にあること
・まっすぐな音の出され方をお手本として聞いたことがあること
・自分の演奏がまっすぐではなく後押しになっている自覚(吹きながら、あるいは録音で)
これが揃っていれば、あとは「機能する改善方法」を探す・試すフェーズに入れます。
あるいは実際にまっすぐに変化することで、上記3つのどれかが得られることもあるかもしれません。