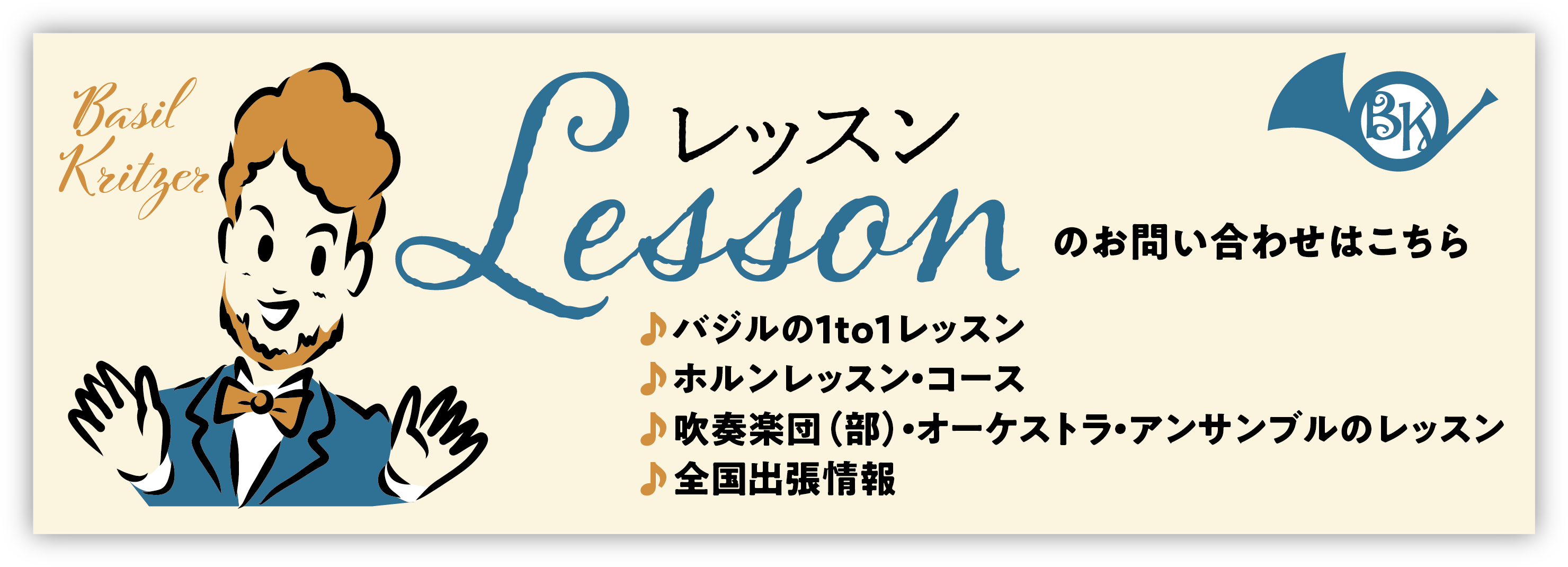普段私のレッスンには、中高年の管楽器演奏愛好家の方がいらっしゃることが多いです。
そういった方々は、演奏するにあたっての体力の低下や、昭和的根性論に基づいた「とにかく頑張って練習する」というアプローチに体がついていかなくなっているのを感じている、そんな方が多い 印象です。
それを踏まえて「効率的なウォーミングアップとは?」という問いについてある角度から考えてみました
とは言いましても私はホルン奏者です。ですからホルン以外の罰金について具体的なウォーミングアップ方法をお伝えするということはできません。
しかし、ホルンの世界においても見渡すと ウォーミングアップのやり方は実に 人それぞれ、千差万別です。
弟子がたくさんいる有名な先生のウォーミングアップパターンをやっている人が多いといったことはありますが、同じぐらい有名な先生であるとウォーミングパターンがまた異なったものになること、そして有名な奏者から有名でない優れた奏者まで見渡していくと、独創的なウォーミングアップパターンも見られます。
何か特定のウォーミングパターンそのものに 特別な効果や他のパターンより優れた効果があるのかどうか?
私は「そんなことはない」という考え方にかなり傾いています。
お経や聖書であれば、そこに書かれている語の一句一句とその列びそのものに特別な力が宿っているのかもしれませんが、教本などに書かれた管楽器のウォーミングパターンそれ自体にそのような特別な力が宿るとは 私はちょっと考えられないわけです。
しかしながら、教本などに書かれたウォーミングアップパターンや基礎練習パターンが、楽器の仕組みや、演奏技術を構成する基礎的な要素の秩序を踏まえて、難易度も 段階的に構成した形で書かれていること もよくあります。
その場合 それをただ順にやっていくだけで何か調子が良かったり、ウォーミングアップが効果的に感じられるということはあるでしょう。
しかしそれは先ほど述べた通り、不思議な力がそこに宿っているということではなく、書き手の理解に基づいて狙いがあって書かれており、その狙いがうまくはまった時に効果が得られるということだと私は考えます。
少々、話が回り道しましたが私がいちホルン奏者にすぎないからこそ、これをお読みの方にはご自身の発案でウォーミングアップ内容を決めていけるような考え方の枠組みを示すことを試みたいと思います。
そのためには、ウォーミングアップだけの話をするわけでもウォーミングアップの話から最初にするわけでもなく、そもそも練習とは?ということの定義付けから始めていく必要があります。
これから、練習・基礎練習・ウォーミングアップをそれぞれ定義していきますが、私が述べる定義が絶対的に正しいということではなく、練習・基礎練習・ウォーミングアップの3つに論理的な繋がりを見出せるようにして、読書ご自身の力で自分自身のための練習とウォーミングアップを構成できるようにすることを一番の狙いとそのための定義付けであることを始めに申し上げておきます。
***
【練習とは?】
定義
「練習とは、自分自身が実現したい演奏を実現するための行動のうち、譜読み・ソルフェージュ及び楽器を使って音を出して行うこと」
この定義に従いまして、譜面の準備や、練習時間を作るための生活の工夫などは練習そのものにはカウントしません。
一方で、楽器を使って音を出していなくても、譜読みをしていたり ソルフェージュして演奏しようとすることが何なのかを明確にしていくことは練習に含めることとします。
また、例えば本番の緊張感に慣れるために会えて誰かに聞いてもらいながら演奏するという状況を作って吹くことや 例えばリサイタルという長丁場で安定した演奏を行うために、敢えて複数回通し練習をするということも、練習に含めることとします。
演奏の状況に応じて自分が実現したい演奏を行うための、楽器を使って音を出す形で行う努力であるからです。
その意味では楽器を使わなくても、イメージトレーニングをするのも 練習に含まれることになります。
***
【基礎練習とは?】
定義
「楽器演奏を成立させる重要な基礎技術を要素別に分けて、あるいは分けずとも基礎技術を把握または意識しながら楽器で音を出すこと」
この定義が意味するところとして、例えば音階練習は基礎練習に含まれるかどうかというところは、基礎技術を把握または意識しながらやっているかどうか次第で変わります。
音階というのは音楽の基礎であることは間違いありません。
しかし管楽器演奏の技術的基礎であるかといえば、どちらかといえばそうではないと考えた方が良いでしょう。
というのも、複数の技術を組み合わせて成立させているはずだからです。
具体的には、例えばアーティキュレーションを加えずにスラーで演奏する場合なら
・音を生み出す技術(発音)
・生み出した音を一定時間生み出し続ける技術(ロングトーン)
・生み出してある音の高さを変える技術(倍音や音域を変える、金管楽器だとリップスラーがそれに相当)
・出したい音が出るような状態に楽器をすること(運指、スライドポジション)
というように。
また、上記の4つの技術的要素は、重要度や難しさは同じではありません。
例えば、音を生み出す技術自体がないと、実現したい演奏を実現するという意味で他のあらゆる技術が発揮できません。例えばそもそも音が生み出せていないと(=発音の技術が成立していないと)音を伸ばすということができない(=ロングトーンできない)ように。
そして音を伸ばせない(=ロングトーンできない)ということは、音階を演奏する中で、倍音/音域を変える技術を持っていても、運指を覚えていてちゃんと実行できていても、音自体がなくなってしまうので、音階が成立しないわけです。
別の言い方をすれば、技術には秩序や階層性があるとも言えるでしょう。その秩序や階層性がどうなっているかということを自分なりに意見を持って、それを踏まえてそれらの技術を意識して音を出すこと。
それが基礎練習 なのです。
・
・
・
こうやって述べるとかなり抽象的で難解に感じた方もいらっしゃる かもしれません。
よく書けている教本というものは、基礎技術の秩序や階層性に基づいて章や練習課題が設定されています。だからうまくいけば、ただただ教本を順にやっていくだけで上達していくのです。
しかし、優れた教本を順にやっても、手ごたえがなかったり行き詰まったりしてしまったという経験を持つ方も読者の方には多数いらっしゃるでしょう。
大学生くらいにもなれば、実のところ、自分なりに技術とは何か?基礎とは何か?ということを仮に定義して、その定義に基づいて 自分の練習の仕方を定め、練習を重ね、重ねた練習が自分が実現したい演奏を実現する方向へ作用しているかどうかを自分で検証する、作用していないように感じるならば定義や練習の内容を見直していく、という取り組みを誰でもやる必要があるのではないかという気がしております。
それをやるのを阻む一番の敵は、自分の外部に決定権を委ねることだと思います。自分で考えたり、考えたことを試したりせずに、書いてあることや 先生に言われたことだけをただただやろうとするのがそれです。
***
【ウォーミングアップとは?】
定義
「演奏・練習・基礎練習を行う前に、練習や 基礎練習の目的を果たす上で必要な心と体の行動」
演奏する前のウォーミングアップは、練習や 基礎練習を通じて「もうできるようになっていること」を「実行できるようにするための事前行動」です。
練習や基礎練習をする前のウォーミングアップは、「できるようになりたいことのための練習を行うえで、練習をする前の事前行動」です。
このように捉えておくと、ウォーミングアップは主に思考や意識を音楽や音に向けていくための行動(ex.瞑想、集中、言葉で考えること減らして音で考えることを増やすetc)と、体の活性を高める行動(ex.呼吸、体ほぐし、体を響かせるために声を出すetc)を指すということが分かります。
これらの行動は、楽器を使ってやってもいいし 楽器なしでやってもよいのです。
***
以上、練習 基礎練習 ウォーミングアップの3つについて 区別して述べてまいりました。繰り返しになりますが これが絶対正しい捉え方だと主張するつもりは全くありません。
これを参考にし、あるいは批判的に理解して ご自身の練習 基礎練習 ウォーミングアップの考え方をより明晰にしていただいたりするためにお役立ていただければと思います。