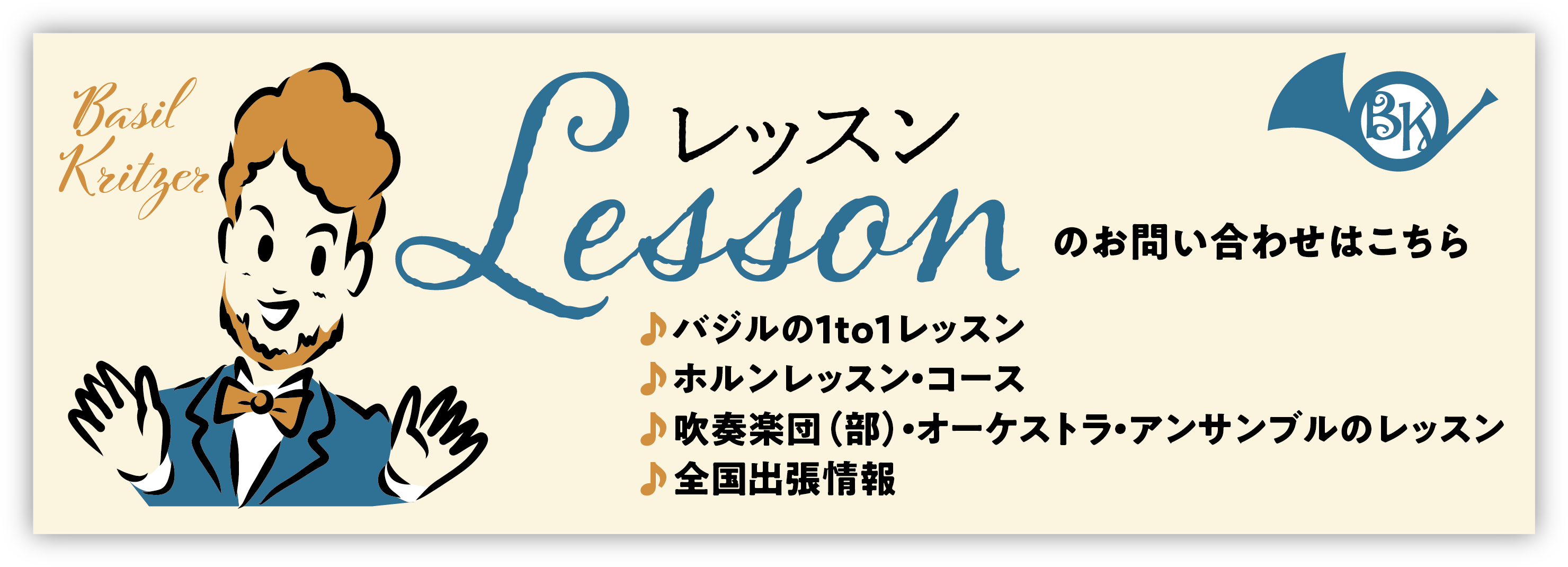吹奏楽指導者の方から質問のメールを頂きました。
***
【質問者】
いつもブログの記事や、YouTubeでのレッスンの動画など、拝見させていただいています。分かりやすく大変勉強になります。ありがとうございます。
管楽器の演奏におけるブレスで質問があります。
先生は、
腹式呼吸は、お腹を膨らませるように息を吸い、そのお腹をキープ(もしくは、さらに膨らませる)しながら吐いていくイメージ
。
胸式呼吸は、胸や肩が上がるのを押し付けないで許しながら、息を吸い、その胸や肩をキープ(胸が下がらないように)しながら吐いていくイメージ。
腹式呼吸と胸式呼吸のどちらかやりやすい方で演奏するのが良いと仰っておりました。
分かりやすく、また、とても理解出来ます。
ただ、私の場合、色々試した結果、
吸う時にお腹が膨らみ、吐く時に胸をキープするブレスが1番力みが無く、調子が良いです。
もちろん、吸う時に全く胸が上がらないわけではありません。お腹、胸、背中が同時に膨らみ(お腹>胸>背中)、吐く時は、腹筋に力を入れてお腹を潰して、それで生まれる息の圧力を胸でさらに支えるようにして吹いています。
とくに高音域はこのブレスの時が1番ストレスが無く音の伸びが良く感じます。
腹式呼吸も胸式呼吸も両方取り入れた呼吸法(ブログで先生が仰っていた全式呼吸?)なのかな、と私自身は思っていて、ストレスなく吹けているので、自分でただ吹く時は、「まぁ、ストレスなく吹けてるし、なんでも良いか!」と言う感じなのですが、
指導をするとなった際に、この呼吸法を説明して良いものか、また、どのように説明するか迷っています。
文章が長くなってしまい申し訳ないですが、
①私のイメージしている呼吸法は変なのか
変ではないのであれば、
②腹式呼吸と胸式呼吸を同時に行い、どちらの要素が大きいか、その比率によって自分に取って最適なブレスを探すのが良い。
という説明は正しいか。
先生のお考えを、お答え頂ければ幸いです。
✨✨✨
【バジル】
この度はご質問のメールを頂き有難うございます。
まず、②についてお答えします。
私は、特定の呼吸法を教えるという考え方も、自分の呼吸法を教えるという考え方も取らず、
・ベストな呼吸法は人により異なり
・何がベストかを決められるのは本人だけ
と考えます。
従って、
『どうしたら、自分にベストの呼吸法を探すことができるか?』
を考えます。
ひとつは、いろんな人の呼吸法を学ぶというアプローチがあると思います。
質問者さんの①の呼吸法のイメージは質問者さんのものですから、それを学んで取り入れたり、合わないと判断して取り入れないことにしたりして学ぶこともできます。
もうひとつは、呼吸法の枠を大きく取ってみることです。
・吸う
・吐く
・支える
が呼吸法の軸とすると、
・体のどのあたりで吸うか、吐くか、支えるか
・どれぐらい吸うか、吐くか、支えるか
・どれぐらいすることを意識するか
いずれについても、場所や量に関しての選択肢がグラデーションであるわけです。
私はそういう見方をしますので、その見方から見ると、質問者さんのおっしゃっている呼吸法というのは、支えている場所が胸とお腹の間ぐらいの箇所なのかなと想像します。
ただ、吹いている本人の感覚的実感と、外から見た場合の動きの状況というのは、言葉にすると一致しない場合があります。
なので、外から見た時の状況を言葉で描写するとどうなるか、については実際に演奏のご様子を拝見しないと分かりません。
いかがでしょうか?
✨✨✨
【質問者】
早速のご回答ありがとうございます。
》》場所や量に関しての選択肢がグラデーションであるわけです。
この言葉を聞くことができて、少し安心しました。
先生のレッスンの動画を見ていて、腹式呼吸はこう。胸式呼吸はこう。比べてみて良い方を選択しよう。とレッスンしている場面があり、私がそこだけを切り取って考えてしまい、考えが凝り固まっていたのかもしれません。
指導の際は、あくまで私の呼吸法として、紹介をしてみようと思います。
また、私も楽器を吹き始めてからずっとこの呼吸法でやってきたわけではないので、昔どうだったか。記憶のある範囲で、何故このようなブレスになっていったのか、また、骨格や体格は人により異なり、正解の呼吸法は一つではないことも合わせて伝えてみようと思います。
また、何か不安になったり分からないことが出てきたら、質問をさせていただくことがあるかもしれません。ありがとうございました。
✨✨✨
【バジル】
胸式呼吸「は」こう
腹式呼吸「は」こう
だけれど呼吸法は、その2つだけではないということです。
呼吸法のちがいの一つは支える場所のちがいである、と定義するとすれば、呼吸法は微妙な違いとしては無数に種類があることになるわけです。
この無数の呼吸法を2種類に分類すれば腹式と胸式になるわけですが、その2種類の分類法でもちょうど間ぐらいのやつが出てきます。
それに名前を与えれば(横隔膜式呼吸、真ん中呼吸、赤道呼吸など如何様にも名付けようがあります)、この時点で2分類ではなくなります。
2分類でなくなったなら、別に3分類にとどめる必要も特にはないわけです。
分類方法は、分類するということをどういう用途で用いるかによって結構いくらでも変えられると思います。
参照
県西レッスンvol.3【4つの呼吸法を比べて試そう!】
【呼吸法の種類】 磐田東高校吹奏楽部レッスン④
【金管奏法立体マトリックス】
【楽器奏法・身体運用の決定権】その5